隠れ家が、隠れ家ではなくなった日 -Instagramが変える街の景色-

普段は近所の常連客しか立ち寄らないのではないかと思われる小さなコーヒー屋さんが、突然、平日の昼過ぎにもかかわらず行列の出来る店になりました。嬉しいことなのかも知れませんが、お店のキャパシティを超えているのではないかと見える光景は、このまちの「らしさ」とは少し違うような気もします。
渋谷から坂を下り八幡通りの嶺を超えてキャッスルストリートまで。ひと呼吸つきたいところなので、アイスコーヒーを飲ませてもらいに立ち寄ってみると、女性の二人組が二組、店の前の小さなベンチでメニューを見ながら品選び。一組はオーダーが決まって、狭い階段を上って上の階へ。空いたところに座らせてもらいアイスコーヒーが出来るのを待っていると、また女性の二人組がやってきました。
この店では、常にハンドドリップでコーヒーを淹れてくれるので、出来上がりまでにはそれなりの時間がかかるのは承知の上ですが、店先でバリスタ君がサーバーに落としていたコーヒーは階段を上がって上の階に消えて行きました。一組の女性客が階段を下りてきたのと入れ替えに、下でメニュー選びをしていた二人組が階段を上って行く間に、さらに二人組が到着。まだ、私のコーヒーは出てこない。向かいの店の馴染みの店主が煙草を吸いに出てきたので、挨拶がてら一服のお付き合いへ。見ていると、さらに一組の女性客が。続いて女子高生の一組も。
二本目も吸い終わる頃、やっとバリスタ君がコーヒーを手渡しに出てきてくれました。
そもそもこの店は、自家焙煎しているコーヒー豆の販売所という役割が大きく、1階には大きな焙煎機が鎮座し、その周りには大量の輸入されたコーヒー豆の袋が積み上がっていて、コーヒー豆の販売をおこなう店頭の狭いスペースでハンドドリップのコーヒーは淹れてくれるというようなお店ですが、2階にはフロアの7割ほどの面積にエスプレッソマシーンを置いたカウンターが設えられていて椅子は無く、基本的にはテイクアウト中心のコーヒースタンドと考えた方がよいお店です。しかし、最上階にはアトリエというコンセプトだからでしょうか、全面が白で統一された内装のフロアにほんの数席の椅子とテーブルが用意されています。
「行列の出来る店」でも書きましたが、今やInstagramの影響力は極めて大きく、普段は近所の常連客しか訪れないような場所も、予期せずして行列の出来る店になってしまいます。
Instagramでの「映え」が狙えるフォトジェニックなポイントは、全面ガラス張りの壁面の前に置かれた一組のテーブル席だけです。運よくそのテーブルが空いている時に行けなかった女子は、また運試しをしてみるのかもしれません。
2017年の操業以来、急速に事業を拡大しているファッションメディアに「RiLi.tokyo(リリドットトーキョー)」があります。2019年3月末には1億円の資金調達を実現した株式会社RiLiは、もともとはマークスタイラー出身の渡邉麻翔さんが、キュレーションサイト「MERY」の不祥事の後、そのポジションを埋めるメディア事業としてスタートしたということですが、掲載された商品の販売をおこなったところ即座に完売したことからECショップもスタートしたというものだそうです。事業分野としては、最近注目されている、情報メディアとネット通販を組み合わせたビジネスモデルである「メディアコマース」のひとつに位置づけられると思います。2019年11月の時点でインスタグラムアカウント:https://www.instagram.com/rili.tokyo/のフォロワー数は25万3,000人になっているそうです。
しばらく前からこのサイトには注目していたところ、少しづつ代官山の店舗でも取り上げられるところが出てきていました。
2020年7月18日にこのお店が紹介されていたので、たぶんこの日の状況はその影響によるところが大きいのではないかと推測しています。
RiLi.tokyoでは、2017年の操業当初に「Instagrammer News」でRiLiオフィシャルメンバー募集をおこなっています。
RiLiオフィシャルメンバーとは…
RiLiが主催する審査制インスタグラマーコミュニティ
メンバーのインスタグラムからネタと写真をPICK→記事にして発信
写真が採用されるごとに掲載料(¥100~)がもらえる
オフィシャルメンバーは審査制です。
メンバー登録には審査を通過していただく必要があります
となっています。
RiLi.tokyoで投稿写真がシェアされているインスタグラマーを見ると、1,000人程度のフォロワーを持つ人から万人単位のフォロワーを持つ人まで、幅広いフォロワー数を持つインスタグラマーがRiLiオフィシャルメンバーになっているようです。
渡邉麻翔さんはあるインタビューの中で、「少し前まで、ファッションは「渋谷系・原宿系・丸の内系」などの街や「CanCam系・NYLON系」といった雑誌の名前でカテゴライズされてきました。しかし、利便性や話題性といった経済合理性が優先された結果、最近は街や雑誌がコモディティ化している。ファッションを定義するものがなくなりつつあるんですよね。」「街や雑誌が均質化したことで、若者は「自分は何系なのか」というアイデンティティを持ちづらくなっている」と語っています。
また、RiLiのスタッフである瓜生さんは別のインタビューの中で、「RiLiの目標は、同じ世界観を持つ人が集う街や雑誌のようなコミュニティをつくりたいということです。」と語っています。
これが2020年の現実であると認識する必要があるのでしょうが、代官山だけはコモディティ化せずに同じ世界観を持つ人が集う街であり続けることを期待したいとは思っています。
インスタグラムビューワーの「picuki.com」でこのお店を見てみると、現在も連日のようにインスタの投稿が上がっているようです。
いっときのこの熱が冷めるのはいつ頃だろうか…と思いつつ、しばらくは待たされることを覚悟しなければならなくなったある夏の日でした。
関連記事
行列のできる店

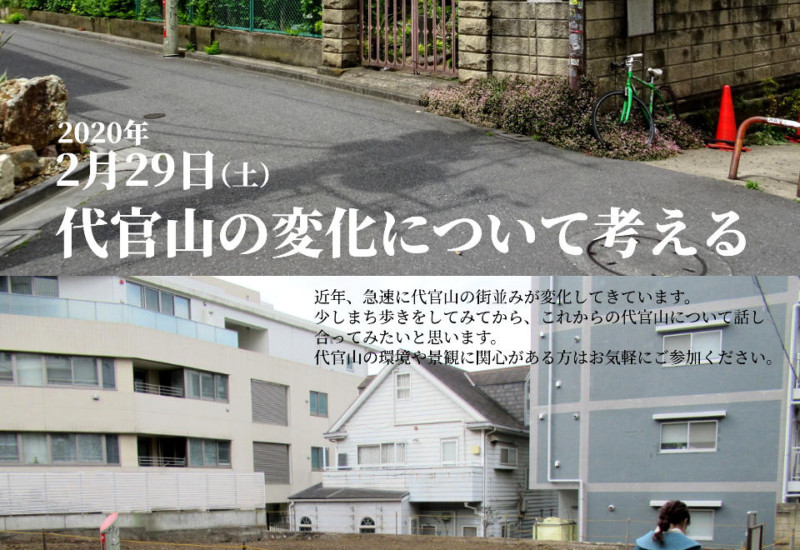


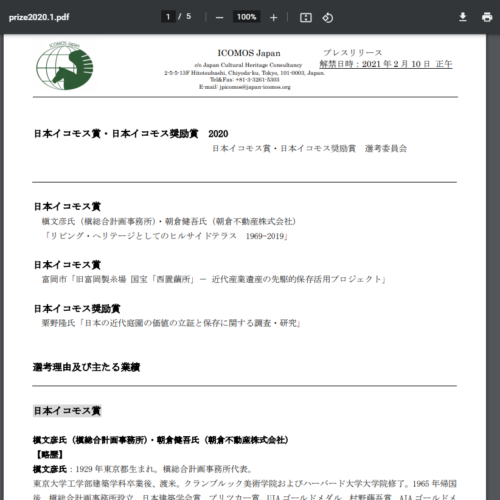


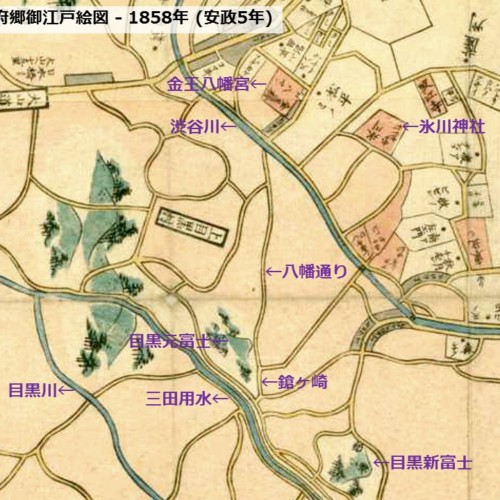

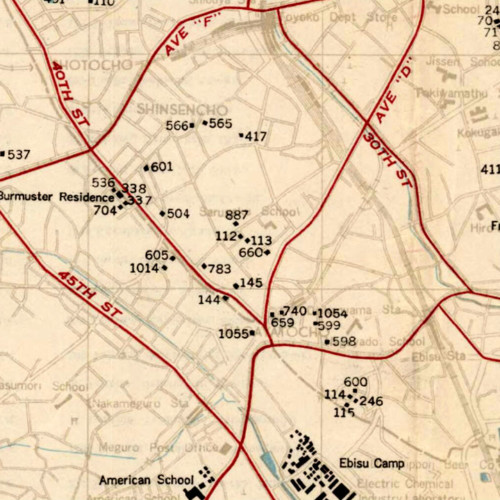


この記事へのコメントはありません。